問題9
環境基本法の基本理念に関する記述中、ア~エの( )の中に挿入すべき語句の組合せとして、正しいものはどれか。
環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び( ア )が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の( イ )である限りある環境が、人間の活動による環境への( ウ )によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の( エ )を享受するとともに人類の存続の( イ )である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。
| 選択肢 | ア | イ | ウ | エ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自然環境 | 基本 | 負荷 | 恩恵 |
| 2 | 生態系 | 基盤 | 負荷 | 恵沢 |
| 3 | 自然環境 | 基盤 | 影響 | 恩恵 |
| 4 | 生態系 | 基本 | 負荷 | 恩恵 |
| 5 | 自然環境 | 基本 | 影響 | 恩恵 |
(令和4年)
問題9の解答
正解は「2」です。
問題9の解説
環境基本法第三条に関する問題です。条文は以下のとおりです。
第三条 環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。
e-gov 法令検索より引用
公害防止管理者の試験では、第三条はよく出るので覚えておくことをおすすめします。その上で、それぞれの言葉の背景について解説していきます。
生態系とは、特定の環境に生息するすべての生物とそれらを取り巻く水・大気・土壌などの非生物的環境が相互に影響し合ってまとまった一つのシステムを意味しています。一方で、自然環境は、生物が関わらない非生物的な要素(光、水、大気、土壌など)と生物的な要素(植物、動物など)を合わせた全体を指しているので、生態系よりも概念として広いです。
- 「自然環境」=山・川・空などの広い概念。必ずしも“バランスで成り立つ”とは限らない。
- 「生態系」=バランスや相互作用を前提とした仕組み。条文のニュアンスにピッタリ。
どちらも微妙な均衡によって成り立つと言えそうですが、条文では「生態系」というシステムに焦点を当てられています。覚えるしかない問題です。
ここに入るのは 基盤 です。基盤とは「土台・ベース」という意味で、人間の健康で文化的な生活が成立するための根本条件を指します。
- 「基盤」なら「存続の土台」となり、条文の厳格さに合う。
- 「基本」だとニュアンスが弱く、法令用語としても不自然。
条文ではプラスとマイナスの両方を含む「影響」ではなく、マイナスのニュアンスを持っている「負荷」を使います。
例えば、工場排煙が大気への負荷、農薬散布が水・土壌への負荷など人間の社会経済活動は環境に何かしらのネガティブな影響をもたらす可能性があり、それを「環境への負荷」と表現しているのです。
ここで重要なのは「法律独特の言い回し」です。一般的には「恩恵を享受」と言いたくなりますが、環境基本法や他の環境関連法令では 「恵沢」 が使われます。覚えるしかない問題の一つです。
- 「恩恵」=日常語としては自然。
- 「恵沢」=法律用語。自然から得られる利益や幸せを厳格に表すための定型句。
本条文の要点

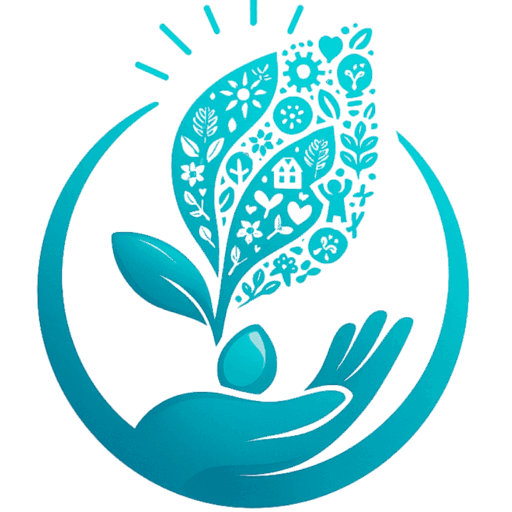









コメント