問題2
環境基本法第16条に規定する環境基準に関する記述中、ア~ウの( )の中に挿入すべき用語(a~e)の組合せとして、正しいものはどれか。
政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の( ア )について、それぞれ、人の健康を( イ )し、及び生活環境を( ウ )する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
- a.支障
- b.保護
- c.保全
- d.条件
- e.確保
| 選択肢 | ア | イ | ウ |
|---|---|---|---|
| 1 | a | e | d |
| 2 | a | b | c |
| 3 | d | b | e |
| 4 | d | b | c |
| 5 | d | c | e |
(令和6年)
問題2の解答
正解は「4」です。
問題2の解説
公害防止管理者試験の公害総論では、環境基本法の条文に関する問題が出題されます。
まず、問題2で引用されている環境基本法第十六条の条文は以下のとおりです。
第十六条 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
e-gov 法令検索より引用
2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、次の各号に掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。
一 二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるもの 政府
二 前号に掲げる地域又は水域以外の地域又は水域 次のイ又はロに掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 騒音に係る基準(航空機の騒音に係る基準及び新幹線鉄道の列車の騒音に係る基準を除く。)の類型を当てはめる地域であって市に属するもの その地域が属する市の長
ロ イに掲げる地域以外の地域又は水域 その地域又は水域が属する都道府県の知事
3 第一項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。
4 政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの(以下「公害の防止に関する施策」という。)を総合的かつ有効適切に講ずることにより、第一項の基準が確保されるように努めなければならない。
環境基準に関する条文であり、各項の趣旨を含めて理解しておくことを推奨します。
「条件」 (d)
環境基本法第十六条は、「環境基準」について定めています。答えには、基準を満たすために必要なことを示す「条件」が入るわけですが、その意図は「大気、水質、土壌、そして騒音に関する環境がどういう状態なら人の健康を保護し、生活環境を保全できるのか?」という問題に対して、具体的な内容を定めることにあります。基準を守るためには条件の設定が必要不可欠なわけです。
「保護」 (b)
ヒトの健康に関しては「守る(保護)」という表現を使うのが法律的に正確です。一方で、「保全」や「確保」は環境や状況などのモノやコトを維持するニュアンスで、人の健康には使いません。
「保全」 (c)
「生活環境を保全する」とは、今ある良い環境を保って守るという意味です。自然や生活環境とセットで使用される条文の定番でもあるので覚えておきましょう。「確保」という言葉は「確実に手にいれる」という意味であり、資金や資源などの物理的な対象に対して使用するのが一般的です。
本条を噛み砕くと、次のように整理できます。

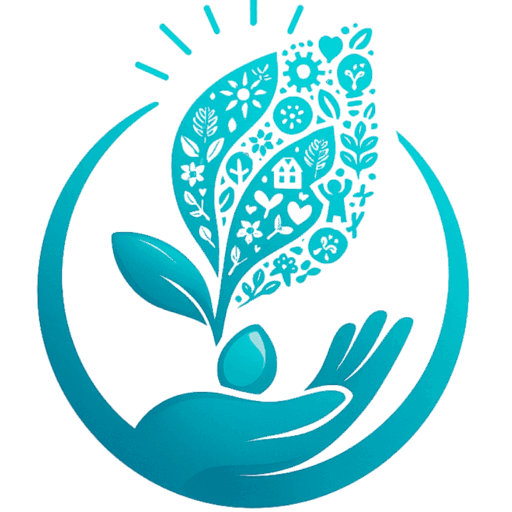









コメント