問題10
環境基本法に規定する環境基準に関する記述中、下線部分(a~j)の用語の組合せとして、誤りを含むものはどれか。
- (a)政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る(b)環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で(c)維持されることが(d)望ましい基準を定めるものとする。
- 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、次の各号に掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。
- 二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって(e)政令で定めるもの (f)当該地域又は水域が属する都道府県の知事
- 前号に掲げる地域又は水域以外の地域又は水域次のイ又はロに掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
- (g)騒音に係る基準(航空機の騒音に係る基準及び新幹線鉄道の列車の騒音に係る基準を除く。)の類型を当てはめる地域であって市に属するもの (h)その地域が属する市の長
- イに掲げる地域以外の地域又は水域 (i)その地域又は水域が属する都道府県の知事
- 第1項の基準については、(j)常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。
- a、c
- b、d
- e、f
- g、i
- h、j
(令和3年)
問題10の解答
正解は「3」です。
問題10の解説
この問題は、環境基本法第16条(環境基準) の内容を正確に理解しているかを確認する定番問題です。
誤りの箇所は (e)・(f) の組み合わせにあります。条文は以下のとおりです。
第十六条 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
e-gov 法令検索より引用
2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、次の各号に掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。
一 二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるもの 政府
二 前号に掲げる地域又は水域以外の地域又は水域 次のイ又はロに掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 騒音に係る基準(航空機の騒音に係る基準及び新幹線鉄道の列車の騒音に係る基準を除く。)の類型を当てはめる地域であって市に属するもの その地域が属する市の長
ロ イに掲げる地域以外の地域又は水域 その地域又は水域が属する都道府県の知事
3 第一項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。
4 政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの(以下「公害の防止に関する施策」という。)を総合的かつ有効適切に講ずることにより、第一項の基準が確保されるように努めなければならない。
条文の主語は「政府」です。よく混同されるのが「国」です。
両者の概念には以下のような違いがあります。
- 国(nation) … 国民・領土・主権を持つ存在全体。
- 政府(government) … 国家を運営する組織。政策の立案・実行主体。
環境基準を定めるのは立法や行政権を担う「政府」です。法律の文言で「国」と書くと、国家全体や国民を含む抽象的な存在を指すことになるため不適切です。
ここでいう「環境上の条件」とは、「大気・水質・土壌・騒音などの環境の質的な状態」を指します。この表現が法律上重要なのは、環境を単に「自然」や「物」として捉えるのではなく、「人の健康」や「生活環境」を守るために保つべき状態(コンディション)」という概念に置き換えている点です。
つまり「環境上の条件」とは、「環境そのものの性質ではなく、健康で文化的な生活を守るために保つべき基準値」を示す法律用語なのです。
条文中では「確保される」ではなく「維持される」という表現が使われています。この違いには明確な法的意味があります。
- 確保される … まだ存在しないものを新たに手に入れるニュアンス。
- 維持される … 既にある良好な状態を保ち続けること。
環境基準は「新しく作る」ものではなく、「今ある環境の良好な状態を守る」ための指針です。したがって、「維持」が適切な表現になります。
環境基準は法律上の「強制的な規制値」ではなく、国の目標値 です。例えば、公害防止法や大気汚染防止法などの「規制値(法的拘束力あり)」とは違い、環境基準は「行政が努力して守るべき水準」です。このため条文では「守らなければならない基準」ではなく、「維持されることが望ましい基準」という“努力目標”として表現されています。
「政令で定めるもの」とは、複数の都道府県にまたがる地域や水域のうち、環境基準を指定する必要がある特定の区域を政令によって定義できる という意味です。
これは、全国一律の法律(環境基本法)において、個々の事情(地形・気候・産業構造など)を柔軟に対応させるために、政令(内閣が定める命令) に委任しているのです。
ここがこの問題の誤りポイントです。条文では、「二以上の都道府県にわたる地域又は水域であって政令で定めるもの」についての指定権者は『政府』 となっています。その理由は以下の通りです。
- その地域が複数の都道府県にまたがるため、個別の知事では調整ができない。
- したがって、国全体として調整・管理する必要があるため、中央政府(環境省)が担う。
つまり、「地方ではなく、国レベルの調整・責任が必要な範囲」であるため、「都道府県知事」ではなく「政府」が正しい指定者となります。
環境基準の対象には、大気・水質・土壌に加えて「騒音」も含まれています。そのなかで、「市に属する地域の騒音基準」は特に例外的に独立した取り扱いがされています。
これは、市が生活環境に密着した行政を担うため、地域ごとの実態に合わせた細かい調整(道路・住宅・工場などの立地関係)が必要だからです。
市に属する地域の騒音基準は、その地域を最もよく把握している「市の長(=市長)」が指定します。このルールの背景は「地方分権と現場主義」です。都道府県よりも現場に近い自治体(市)が、住民の生活環境を守る主体となるよう設計されています。
一方、市に属さない地域の指定権者は「都道府県知事」です。
環境基準の指定権限は次のように整理できます。
| 区分 | 指定権者 |
|---|---|
| 二以上の都道府県にまたがる地域 | 政府 |
| 市に属する地域(騒音基準) | 市長 |
| その他の地域・水域 | 都道府県知事 |
環境基準は科学の進歩に応じて常に見直されるべきものであると明記されています。かつて存在しなかった環境問題(例:PM2.5、微小粒子状物質、光化学スモッグなど)に対応するため、科学的知見が進歩するたびに環境基準は改定されてきました。環境基準は「固定的な数値」ではなく、最新の科学による判断を反映する「生きた基準」なのです。
本条を噛み砕くと、次のように整理できます。

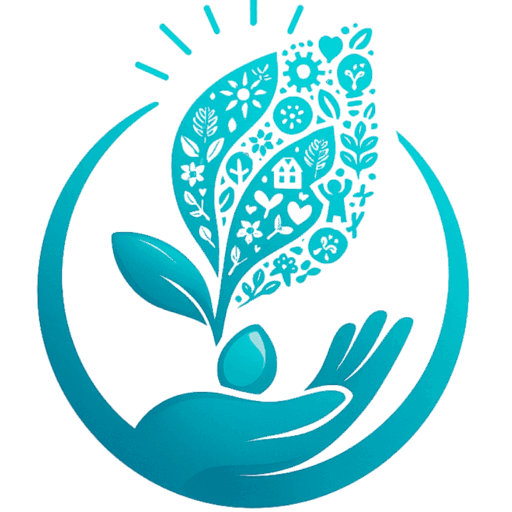









コメント