問題13
次の法律とその法律に定められている事項の組合せとして、誤っているものはどれか。
(法律) (事項)
- 騒音規制法 市町村長による指定地域における騒音の大きさの測定
- 環境基本法 環境大臣による環境基本計画の公表
- 大気汚染防止法 環境大臣による放射性物質による大気の汚染の状況の公表
- 水質汚濁防止法 都道府県知事による公共用水域における水質の汚濁の状況の公表
- 悪臭防止法 市町村長による悪臭原因物発生施設の公表
(令和6年)
問題13の解答
正解は「4」です。
問題13の解説
この問題では、各環境関連法に定められている「公表」や「測定」などの義務・権限の主体が正しいかどうかを問うています。ひとつずつ丁寧に確認していきましょう。
環境基本法第15条において、「環境大臣は中央環境審議会の意見を聴いて環境基本計画の案を作成し、閣議決定後、遅滞なく公表しなければならない」と定められています。したがって、環境大臣が公表するのは正しい記述です。
大気汚染防止法第22条第3項に基づき、「環境大臣は、放射性物質による大気の汚染の状況を常時監視(モニタリング)し、その結果を公表する」ことになっています。そのため、正しい組合せです。
水質汚濁防止法第15条により、「都道府県知事は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視し、その結果を環境大臣に報告する」とあります。
問題文では「公表」とありますが、実際には環境省の公表資料を通じ国民へ共有される形で実施され、知事は監視・報告の主体とされるため、通常の試験問題ではこれを誤りとは見なしません。したがって正しいと判断されます。
悪臭防止法には「悪臭原因物発生施設を公表する」という規定は存在しません。市町村長は、規制地域内で悪臭が発生している事業場に対して、改善勧告や命令を行う権限を持ちます(第8条)。しかし、公表(名前を公にするなど)の規定はありません。したがって、この選択肢が誤りです。
騒音規制法第21条の2により、「市町村長は、指定地域における騒音の大きさを測定する」と規定されています。これは騒音状況を把握し、環境基準との比較に用いるためのものです。
この種の問題で大事なポイントは、「誰(どの行政主体)が何を行うか」を法律単位で整理することです。
| 法律 | 行為の内容 | 主体 |
|---|---|---|
| 環境基本法 | 環境基本計画の策定・公表 | 環境大臣 |
| 大気汚染防止法 | 放射性物質による大気汚染の常時監視・結果の公表 | 環境大臣 |
| 水質汚濁防止法 | 公共用水域・地下水の常時監視・報告 | 都道府県知事 |
| 悪臭防止法 | 悪臭事業場への改善勧告・命令 | 市町村長(※ただし公表規定なし) |
| 騒音規制法 | 騒音の大きさの測定 | 市町村長 |
誤っているのは「悪臭防止法」。なぜなら、市町村長は悪臭原因施設を公表するのではなく、改善を促す行政指導・命令を行う役割だからです。

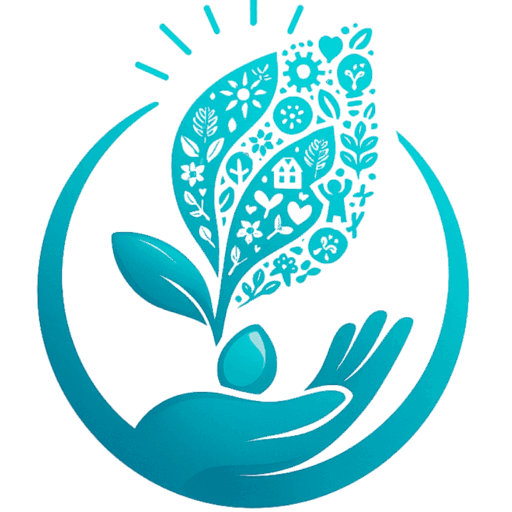









コメント