
公害防止管理者試験の過去問|公害総論:環境基本法に関する問題⑪

問題11
環境基本法に規定する定義に関する記述中、下線を付した箇所のうち、誤っているものはどれか。
この法律において(1)「環境への負荷」とは、(2)環境の保全上の支障のうち、事業活動(3)その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、(4)水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第二十一条第一項第一号において同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、(5)地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(令和2年)
問題11の解答
正解は「1」です。
問題11の解説
本問題では、環境基本法第二条が使用されています。条文中に定められた「環境への負荷」の定義は、環境法の根幹にあたる重要な部分です。用語の意味と、他の定義(環境の保全・公害・生活環境など)との違いを整理して覚えましょう。
第二条 この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
e-gov 法令検索より引用
2 この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
3 この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第二十一条第一項第一号において同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
その上で、それぞれの正誤に関する背景について把握してきましょう。
「環境への負荷」は “まだ被害は起きていないが、環境に悪影響を与えるおそれのある行為や状態” を指します。一方、問題文のように「相当範囲にわたる汚染や被害が生ずること」と書いてあるのは、第2条第3項『公害』の定義 です。
| 用語 | 意味 | キーワード |
|---|---|---|
| 環境への負荷 | 原因側の影響。被害を起こすおそれ。 | 「おそれがある」 |
| 公害 | 結果としての被害。 | 「被害が生ずること」 |
したがって、(1)は「公害」の定義を「環境への負荷」としてしまっている点で誤りです。
この表現は、第2条第3項(公害の定義) に正確に登場します。ここでいう「環境の保全上の支障」とは、
大気や水質などの環境が悪化して、人の健康や生活環境に悪影響を与える状態のことを指します。「環境が守られない状態=支障がある状態」を表現しています。
これは条文どおりの表現です。環境基本法では、汚染の原因が「企業活動」に限らないことを明示しています。つまり、個人の生活行動(車・家庭排水など)も“環境への影響”に含まれるということです。
この点が旧・公害対策基本法との違いで、「企業だけでなく、社会全体が環境への責任を負う」という考え方を示しています。
これは条文そのままの記述です。法律では「水質汚濁」を非常に広く捉えています。単に化学的な汚れだけでなく、水温の変化(温排水) や 底泥の堆積(ヘドロ化) といった状態悪化も含まれます。「水の質」だけでなく「水環境全体の健全性」が守るべき対象なのです。
この表現も条文どおりです。つまり、地盤沈下が「自然現象」や「鉱山採掘」によって生じた場合は、公害とは扱われません。しかし、地下水の過剰な汲み上げなどによる沈下は「人間活動に起因する公害」として対象になります。例えば、工場などが地下水を大量に使い、地盤が沈下すると、建物傾斜や浸水リスクが発生sいます。これが公害としての地盤沈下の例です。
本条を噛み砕くと、次のように整理できます。

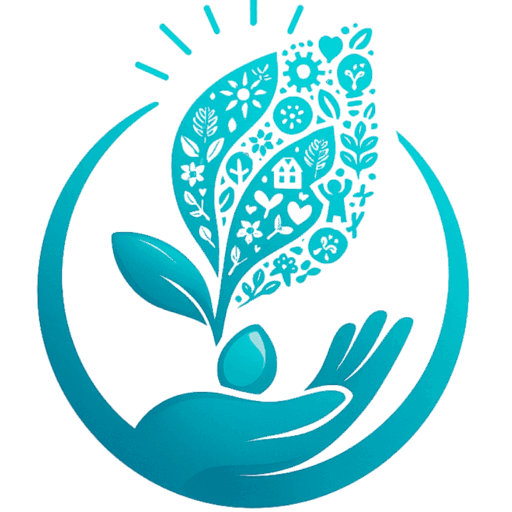








コメント