
公害防止管理者の過去問|令和4年 公害総論 問2 問題と解説
問題2
環境基本法に規定する環境基準に関する記述中、下線を付した箇所のうち、正しいものはどれか。
(1)国は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で(2)確保されることが望ましい基準を定めるものとする。
2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、次の各号に掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。
一 二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるもの (1)国
二 前号に掲げる地域又は水域以外の地域又は水域次のイ又はロに掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 騒音に係る基準(航空機の騒音に係る基準及び新幹線鉄道の列車の騒音に係る基準を除く。)の類型を当てはめる地域であって市に属するもの (3)その地域が属する都道府県の知事
ロ イに掲げる地域以外の地域又は水域 (4)その地域又は水域が属する市の長
3 第一項の基準については、(5)常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。
4(略)
問題2の解答
正解は「5」です。
問題2の解説
残念ながら、この問題は条文を暗記することが求められています。問題6で引用されている環境基本法第十六条の条文は以下のとおりです。
第十六条 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
e-gov 法令検索より引用
2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、次の各号に掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。
一 二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるもの 政府
二 前号に掲げる地域又は水域以外の地域又は水域 次のイ又はロに掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 騒音に係る基準(航空機の騒音に係る基準及び新幹線鉄道の列車の騒音に係る基準を除く。)の類型を当てはめる地域であって市に属するもの その地域が属する市の長
ロ イに掲げる地域以外の地域又は水域 その地域又は水域が属する都道府県の知事
3 第一項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。
4 政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの(以下「公害の防止に関する施策」という。)を総合的かつ有効適切に講ずることにより、第一項の基準が確保されるように努めなければならない。
その上で、それぞれの正誤に関する背景について把握してきましょう。
条文では「国」ではなく「政府」となっています。両者は混同しやすいですが、概念として明確に違いがあります。国は「特定の領土とそこに住んでいる人たちの集合体」です。一方で、政府は「国を統治する仕組み」を指しています。
厳密に言えば、政策を立案する立場は「統治機構」であって、「集合体」ではありません。したがって、「政府」がより適切な表現であると言えます。話し言葉では、「国」を主語として政府について語られることがあるので、間違えないように注意してください。
確保は「新しいものを確実に手にいれる」というニュアンスを示す言葉です。「ない状態からある状態」という0と1の発想ではなく、環境基本法では「今ある状態を保つ」ために必要なことを定めています。そのため、「維持」が適切な表現なのです。
市に属する地域の騒音基準は「その市の長」が指定します。都道府県の知事ではありません。権限に関することがルールとして覚えるしかありませんが、市に属する地域の騒音基準を市長が決定するのは論理的に自然であると言えます。
「イ=市の騒音地域は市の長」と「ロ=それ以外は都道府県知事」という役割分担になっています。県内に存在するが特定の市区町村が負えない責任の範囲を「都道府県の知事」が担当するのは理にかなっています。
環境基準は一度決めたら終わりではなく、科学の進歩や社会の変化に応じて見直す必要があります。例えば、昔は「PM2.5」という概念はありませんでしたが、今は基準が存在します。すなわち、科学的に新しい知見が出たら、基準を適切に改定することが条文に書かれているのです。そのため、「常に適切な科学的判断」という文言は正しいと言えます。
本条を噛み砕くと、次のように整理できます。

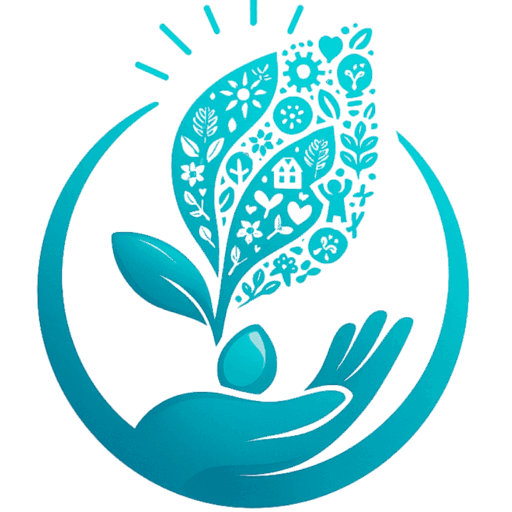








コメント