
公害防止管理者の過去問|令和5年 公害総論 問2 問題と解説
問題2
環境基本法第3条の環境の恵沢の享受と継承等に関する記述中、下線部分(a~j)の用語の組合せのうち、誤っているものはどれか。
(a)環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして(b)確保することが人間の(c)健康で文化的な(d)生活に欠くことのできないものであること及び(e)生態系が(f)微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の(g)基盤である(h)限りある環境が、人間の活動による(i)公害によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の(j)世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の(g)基盤である環境が将来にわたって(b)確保されるように適切に行われなければならない。
- a、c
- b、i
- d、g
- e、h
- f、j
(令和5年)
問題2の解答
正解は「2」です。
問題2の解説
公害総論の試験では、環境基本法の条文内容に関する正誤問題が頻出します。暗記するだけではなく、法律で使用される言葉の性質を適切に理解することで正解を導き出せるようになるので、法律の趣旨を理解することが重要です。
まず、問題4で引用されている環境基本法第三条の条文は以下のとおりです。
第三条 環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。
e-gov 法令検索より引用
環境基本法第三条は「環境の恵沢の享受と継承等」がテーマとなっています。その前提で、確保は「新しく手に入れる・保証する」という意味であり、「持っていない状態から持っている状態になる」という概念です。「環境は悪くなったら、新しい良いものを他所から持ってくれば良い」といった都合の良い性質を持っていません。そのため、「確保」は誤りであると判断できます。
- 維持:「今ある環境を良い状態で保ち続ける」というニュアンス。
- 確保:「新しく手に入れる・保証する」というニュアンス。
公害は典型7公害(大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音・振動・地盤沈下・悪臭)です。人間の活動によって生じる環境リスクは「公害」以外にも、温暖化やオゾン層の破壊などが存在します。したがって、「環境への負荷」という総合的なリスクを説明する言葉を使っており、「公害」という限定的な表現は誤りになります。
本条を噛み砕くと、次のように整理できます。

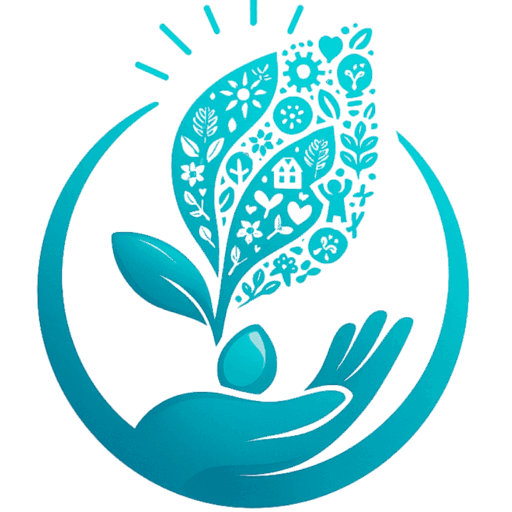








コメント