
公害防止管理者は役に立たない?資格取得のメリットと現場業務との乖離性

公害防止管理者の資格取得を検討するにあたって、「それが本当に役に立つのか?」という実用性が気になる人たちもいるはずです。確かに、資格とは名ばかりで取っても無意味なものもたくさんあります。
実際のところ、公害防止管理者には努力して取得するだけの価値があるのでしょうか?
この記事では、「公害防止管理者は役に立たない?」という疑問について考察しています。また、資格取得のメリットや働き方にも言及しているので、参考にしてみてください。
公害防止管理者は役に立たない?
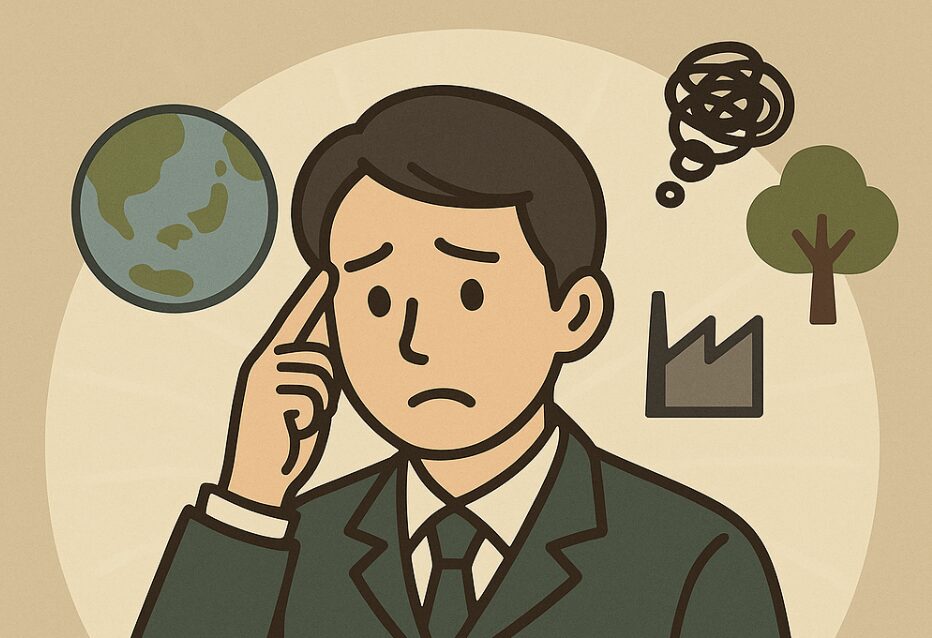
結論から言えば、公害防止管理者は役に立たない国家資格ではありません。
なぜなら、公害防止組織法(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)で明示されている要件に合致する工場では、有資格者から「公害防止管理者」を選任することが法的に義務付けられているからです。公害防止管理者の配置義務に違反すれば罰則もあります。
第四条 特定事業者は、主務省令で定めるところにより、特定工場において次に掲げる業務を管理する者(以下「公害防止管理者」という。)を選任しなければならない。この場合において、第二条第一号又は第二号の特定工場にあつては、政令で定めるばい煙発生施設又は汚水等排出施設の区分ごとに、それぞれ公害防止管理者を選任しなければならない。
e-gov 法令検索より引用
そのため、特定工場に関わる事業を行う場合には、公害防止管理者の資格を持った人が絶対に必要になるため、決して役に立たないとは言えません。むしろ、区分によっては有資格者数が少ないものもあり、その希少性が評価される可能性もあります。
それに加えて、公害防止管理者の選任に手こずっている特定工場も存在しています。環境省が公開した「令和2年度 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行状況調査(令和元年度実績)」では、全国で3,000件以上の未選任工場があると報告されています。
これを踏まえると、日本社会全体として「公害防止管理者の数が足りていない」或いは「適切な配置環境が整っていない」という実態があると言えます。したがって、公害防止管理者の資格は役に立たないどころか必要としている事業所がたくさんあるのです。
公害防止管理者を取得するメリット
さて、公害防止管理者が社会的に役に立つ資格であることを踏まえた上で、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?
ここでは、3つの視点から資格取得の利点について考察していきます。
メリット1 法律上の必置資格として業務の中核を担える
第1に、公害防止管理者の資格を取得することで企業の法的責任を支える中核になれるという利点があると考えられます。
繰り返しになりますが、公害防止管理者は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」(通称:公害防止組織法)で定められた「必置国家資格」です。つまり、一定規模以上の工場や事業所では、法律上この資格を持った人を必ず選任しなければならないと決められています。
たとえば、製造業・化学プラント・発電所・下水処理場などでは、「水質関係」「大気関係」「騒音・振動関係」など、事業内容に応じて有資格者の配置が義務です。このため、資格を持っていれば、工場運営上の法令遵守に係る業務を担うきっかけを得やすくなると考えられます。
メリット2 環境管理・製造業での「スキル証明」になる
第2に、公害防止管理者を持っていることで、環境関連法令を理解している人材として評価される可能性があります。
この資格は、製造業・建設業・環境コンサル業界など幅広い分野で活かせる技術系国家資格です。実際、求人票を見ると「公害防止管理者有資格者歓迎」「資格手当あり」と記載されていることも多く、月1~3万円の資格手当や昇進条件として扱う企業もあります。
また、資格の保有は環境・安全・品質の管理スキルを証明するものでもあるため、転職市場では「環境コンプライアンスに強い人材」として評価され、キャリアの安定と広がりにつながります。
さらに、環境計量士、危険物取扱者、エネルギー管理士などの資格と組み合わせることで、環境・安全・エネルギーの分野を横断的に理解できる「環境管理スペシャリスト」としての価値も高まります。したがって、公害防止管理者の資格は、転職・昇進・スキルアップのいずれにおいても強力な武器になります。
メリット3 環境経営の時代に合致する
第3に、公害防止管理者は「企業の環境経営を支える専門職」として時代に合致した資格です。
近年、企業はCO₂削減や省エネ、廃棄物削減などの取り組みを通じて「環境に優しい企業経営」が求められています。この流れは今後も強くなっていくと考えられますから、公害防止管理者の有資格者はその一端を担う重要な役割を果たすものとして期待されていくはずです。
もちろん、ただ単に資格を取るだけで終わるなら、企業にとって便利な存在であるだけに過ぎませんが、環境基本法の趣旨に沿って、公害防止の専門家として環境保全に自主的かつ積極的に貢献するプロフェッショナルとしての資質を磨くことによって活躍できる場が増えていくかもしれないのです。
現場業務との乖離性を指摘する人もいる
しかしながら、公害防止管理者の資格に関する課題として、現場業務との乖離性を指摘する人もいます。これは、「資格」という標準化された知識体系が、現実の個別具体性が対応できないことを物語っていると考えられます。要するに、仕事では役に立たない知識が多いわけです。
けれども、環境保全の担い手を増やすことを重視するならば、まずは国家試験を通じて最低限度の知識を問うので十分であるという考え方もあります。実践との乖離を肯定するわけではありませんが、実技は後から学んでいくのでも良いと思います。これは官民で協働すべき領域になるかもしれません。
むしろ、特定工場ごとに求められる業務が異なる以上、中途半端な実技試験が導入されると、働きながら試験勉強に取り組む社会人にとって大きな負担となり、今以上に合格者が減ってしまうおそれがあります。その意味では、資格取得者向けに実践的な技能を学ぶ機会の提供が鍵になるはずです。
現実の仕事は標準化できるほど画一的ではありませんから、公害防止管理者の国家試験に実務上の役割を求めるのではなく、個別具体的な業務を理解するための補助線として機能させるために必要なことを今後検討することが求められているのではないでしょうか。










コメント